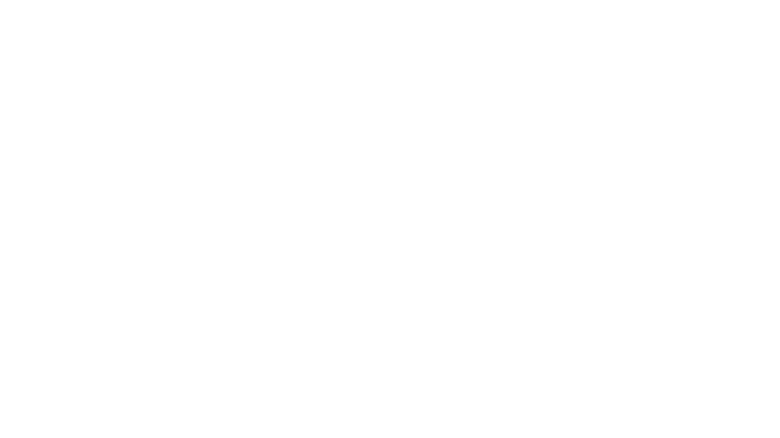
〝A tramp, a gentleman, a poet, a dreamer, a lonely fellow, always hopeful of romance and adventure.〟
――浮浪者、紳士、詩人、夢想家、孤独な人、皆いつでもロマンスと冒険に憧れているんだ。
これは、かの有名な喜劇王 チャールズ・チャップリンの名言だ。彼は、両親の離婚や貧困、ときには生きるために泥棒を働くなど、想像もつかないほど壮絶な幼少期を過ごした。そんな絶望的な日々の中で唯一の楽しみだったのが「演じる」こと。苦しい生活の傍らで俳優斡旋所へ通い、舞台に立つ日を夢見ていた。10代後半のある日、晴れて加入劇団が決まり、劇団入りすると一躍看板俳優に。そのたぐいまれなる才能が敏腕映画プロデューサーの目にとまり、映画俳優としてスカウト。銀幕の世界へと羽ばたいたのだ。
そう、映画とはまさにロマンスと冒険に満ち溢れた“日常の中の非日常”。大画面に映し出される映像は私たちの心を一瞬で引き付け、ありふれた日常から一瞬で引きはがしてくれる。そんな映画は、今やただ「観る」だけのコンテンツではなく「体験する」コンテンツへと変化している。
「3D」によって大きく変化した映画の形
今や家庭用のテレビにまで搭載されている3D技術。映画でも、3D映画は通常より高い価格帯で存在する。3D映画は、専用の3Dグラス(3Dゴーグルともいう)を装着した状態で対応作品を鑑賞すると、文字通り“目の前”で迫力のアクションやカースタントなどを体感できる。
3D映画の歴史は古く、海外(一部日本)では1950年代と1980年代の2回、ブームが訪れている。1950年代、当時としては革新的な発明だったが、各映画館への導入コストの高さや家庭用テレビの普及、なにより今でこそスタンダードなワイドスクリーンの登場によって次第に衰退、表舞台から姿を消すこととなった。1980年代、俗に言う赤青眼鏡が登場。大好評を博した赤青眼鏡の波に乗ろうとハリウッドが次々に3D作品を制作したが、成人向けやホラー、はたまた低予算で作られたチープな作品など万人受けしないものばかり。結果は言わずもがな、影を潜めてしまったのだ。
このように過去2回のブームを経ている3D映画、現在の定着に寄与し、大きな転換期の幕開けとなったのは2000年代になってから。2009年に公開されたジェームズ・キャメロン監督作『アバター』をきっかけとする。初めて映画館で専用の眼鏡をかけ、青い生物が迫ってくる感覚に衝撃を受けた方は多いのではないだろうか。筆者もその一人である。「アカデミー視覚効果賞」や「アカデミー撮影賞」をはじめ、名誉ある賞を総なめにした当作品は、以降の3D映画ブーム、ひいては現在の4Dをはじめとする映像技術に多大なる貢献をもたらした。
「観る」から「体験する」へ
こうして当たり前となった3Dから、映画はさらに進化を遂げている。そこにはただ「観る」だけではない「体験する」姿があった。次に挙げる3つはその代表的な例だろう。
■4DX/MX 4D
4Dの特徴はこれまでの3Dに加え、シアター内に実際に雨や霧、風、雪、泡などを発生させるとともに、シーンに合わせて座席自体が振動。直感的な映像体験を味わえる。一口に4Dと言っても、日本には「4DX」と「MX 4D」の2種類が存在する。とはいえ開発元が異なるだけで大きな違いはないが、MX 4Dの方がシートに搭載された機能が多く、下からの突き上げや首元・背中への感触が鮮明な点などが特徴。ここが僅かな差といえるだろう。ちなみに筆者はどちらも体験したのだが、4DXが好みだ。MX 4Dは機能は多いものの、風や水といった演出にダイナミックさがなく、かつシートもシーンに連動しないことがあった。一方4DXは、機能は少ないもののそれぞれの演出にメリハリがあり、全身で映画を楽しむことができた。これは観る作品によって変化すると考えるため、あくまで個人的な感想として捉えていただきたい。
■IMAX®
IMAX® DMRをはじめとする独自技術によって磨き抜かれた高い映像と音響のクオリティを提供するIMAX®。IMAX® DMRは通常の映画館で上映される35㎜フィルムを、IMAX®シアター用にリマスタリングする技術のことで、不要なフィルムグレイン(フィルム映画らしさのあるノイズ)の除去やカラーリングの調整を経て4K HDR映像の70㎜フィルムへと変換する。特筆すべきはIMAX®シアターだけの空間設計。「The IMAX Experience®」と名付けられた映像体験のために、専用のビッグスクリーンと2台のプロジェクターを使用して映像を投影。座席の距離、座席の角度、音響設備の配置なども緻密に計算されており、ダイレクトに最適化されたUXを体験できる。劇場に赴いて「IMAX®」の文字を見かけた際は、少し割高かもしれないがぜひ体験してもらいたい。
■SCREEN X
正面だけでなく客席の壁面にもスクリーンを配置し、270°の視界で映像を投影する上映技術のこと。人間の横の視野角はおよそ200°(個人差あり)とされているため、どの席に座っても視野に映像が映り、まるで映画の中に入り込んだかのような没入感と臨場感と直に感じることができる。メインの映像は正面に投影されるため壁面を注視することはまずないが、ふと視線を外したときに拡大された映画の世界が広がることは、より高揚感を増してくれるエッセンスになるだろう。
その他にも、「BESTIA」というシアターシステムでは、4Kレーザープロジェクションによってコントラスト比が明確になり、「黒色」の表現が鮮明なHDR映像に。また、天井にもスピーカーを設置し、立体音響を可能にした3D音響システム(イマーシブサウンド)と呼ばれる音響設備が組み合わさることでリアリティを演出している。また、ドルビーデジタルの技術を映画にも応用した「ドルビーシネマ」では、BESTIAやIMAXに勝るとも劣らない輝度やコントラスト比を実現したドルビービジョンを採用。こちらも天井にスピーカーが設置されている。特徴的なのが、入り口に設置されたオーディオビジュアルパスと呼ばれる上映作品の特別映像が流れるスクリーン。上映開始前から気持ち高めてくれる。このようにシアターシステムの技術は多岐にわたる。
また、映像・音響技術だけでなく、映画館における鑑賞方法も多様化していることをご存知だろうか。例えば新宿ピカデリーの「プラチナルーム」。専用のサラウンドスピーカーや最高級ソファが設置されたバルコニー席から映画を鑑賞することができ、入場の一時間前からはまるで高級ホテルのようなラウンジやウェイティングルームでウェルカムドリンクを楽しむことができる。お値段は2名で30,000円。TOHOシネマズでは、映画に没入できるようシアターの目線の位置に「プレミアムボックスシート」を配置(通常料金+1,000円)。革張りの一人用ソファと木目調の肘掛け、荷物置き、サイドには周辺が気にならなくなる仕切りまでもが設置されている。映像をどう表現するかという技術の進歩だけでなく、映像をどう体験してもらうか。両者のたゆみない努力が今日の映像体験を生み出しているといっても過言ではないだろう。
このように、映画は3Dの潮流をはるかに超え、もはやアトラクションと言えるまでに発展し、一般化してきている。昨今、何かと話題に上がる「モノ」から「コト」へのパラダイムシフトは、映画ないし映像技術の進歩にも通ずるものがあるのではないだろか。
「体験する」から「演じる」へ
では、これらの技術が今まで以上に発達するとどうなるのか。「8K映像が主流になる?」「立体音響がよりシャープになる?」確かにそれも可能性としてはあるだろう。では、「映画の主人公になれる」と聞いたらどうだろうか。今から俳優を目指してスクリーンデビューをする、という話ではない。実は現在、誰でも“主演”になれるかもしれない映像技術が実現に向けて動き出しているのだ。
それが、株式会社WOWOWと株式会社stoicsenseが共同開発で進める、世界初の分岐型マルチエンディングVR映画『HERA』。現在、資金調達フェーズで、2021年の公開を目指し活動している。AI技術が人智を超えた未来都市「TOKYO」を舞台に、AIと共生する未来の生活や新しい生き方を描く物語だ。ここまで聞くとありがちなSF映画だと思うかもしれないのが、着目してほしいのが「分岐型」という言葉だ。

本作品で活用されるのが「VR」と「アイトラッキング(視点認証・視線計測)」の技術。アイトラッキングとは、目の動きを捉え「いつ・どこ・どのように」視線が移動したかを解析する技術のことで、いわばゲームのコントローラーにおけるスティックのようなもの。VR空間で体験する映像の中でこの技術を採用することにより、ヒロインや背景、オブジェクト、モブに至るまで、あらゆる視線情報を収集。その視線の動きによって映像が変化する仕組みを搭載することで、ユーザーは“無意識”のうちにストーリーを選択することとなる。つまり、気づかぬ間にストーリーが分岐し、ユーザーによって異なるエンディングを迎えるのだ。
「事実は小説より奇なり」とはよく言うが、自分が“主演”として映画に出演できる未来が約束されていることは、映画ファンのみならず、多くの人々が歓声をあげることだろう。
分岐型については、昨今、増加傾向にある「LIFE IS STRANGE」や「DETROIT BECOME HUMAN」といった分岐型マルチエンディングの「ゲーム」にも触れておこう。ゲームの世界では昔から分岐型マルチエンディングのゲームは存在していた。ではなぜ増加傾向にあるのか。そこには、ユーザーが与えられたものをただ受け取るだけでなく、自ら積極的にゲームに参加し、一体となって物語を紡ぎだす共創型へとトレンドが移り変わっているからかもしれない。
これまでのゲームと言えば、ドットやいかにもゲームだとわかる画質で、決められたストーリーを単一的に進めて同じエンディングを迎えるものが主流、「ゲームの世界だから当たり前だ」とご意見を頂戴するかもしれない。しかしゲームはここ20数年で驚くほどの進歩を遂げている。風景や人物、自然環境などは実写を超えるほどの高画質、もちろん音声も一昔前のピコピコ音ではない。さながら“映画をプレイ”しているかのような錯覚を起こす。画面越しに覗くその世界には、間違いなくそこに暮らす人々がおり、生活を営んでいるのだ。
そんな本物と見まがうほどのゲームの世界で、自分の選択通りにストーリーが進行したらどう思うだろうか。たった一つの選択だけでその世界の住人の生活を180°変えてしまうかもしれない。ときには高揚感を、ときには罪悪感を抱くかもしれない。もはやプレイヤーではなく、“主人公”として物語に入り込めるわけだ。
少し話は逸れたが、映画の“主演”・ゲームの“主人公”として、自らがイニシアチブを握り物語を左右するという点では、両者の違いはほんの数㎝ほどの差でしかないのかもしれない。
真価を見出し、未来へ
現在ではNetflixやHuluをはじめとするサブスクリプションサービスがシェアを広げ、「映画は家で観られる」という時代に入っており、映画館へ足を運ぶことも少なくなったかもしれない。しかし、今回紹介した技術は、そうした映画産業におけるコモディティ化の中で、付加価値を与え、進化しようとしている過渡期としての映画体験と言えよう。こうした体験はいずれ当たり前になってしまうかも知れないが、時流を肌で感じられることにこそ真価があると考える。
それはゲームにも同じことが言える。今は共創型のゲームシステムと映画さながらの壮大な映像美が求められているが、数年もしないうちにある種“スタンダード”なカテゴリとして普及するのではないだろうか。しかし、「当たり前になる前に体感することこそ価値」という考えを当てはめるならば。これもまた真価といえよう。
「観る」から「体験する」、そして「演じる」へ。チャップリンが叶えた銀幕の世界は、私たちのもうすぐそばまで迫っている。技術の革新がさらに発達すれば、映画とゲームの境目が緩やかに混ざりあい、スティーブン・スピルバーグが描いた『レディ・プレイヤー1』のような世界が実現する日もそう遠くないだろう。
分岐型マルチエンディングVR映画「HERA」制作プロジェクト | 株式会社WOWOW
詳しくはこちらから
https://corporate.wowow.co.jp/hera/

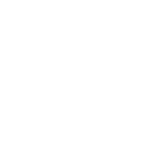

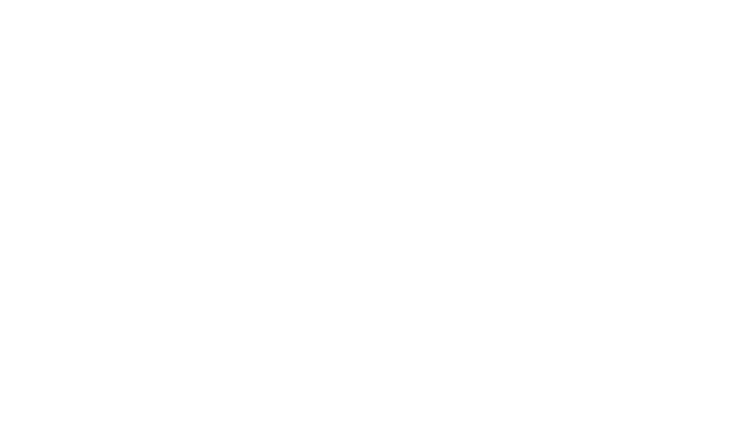
すべてのコメントを見る